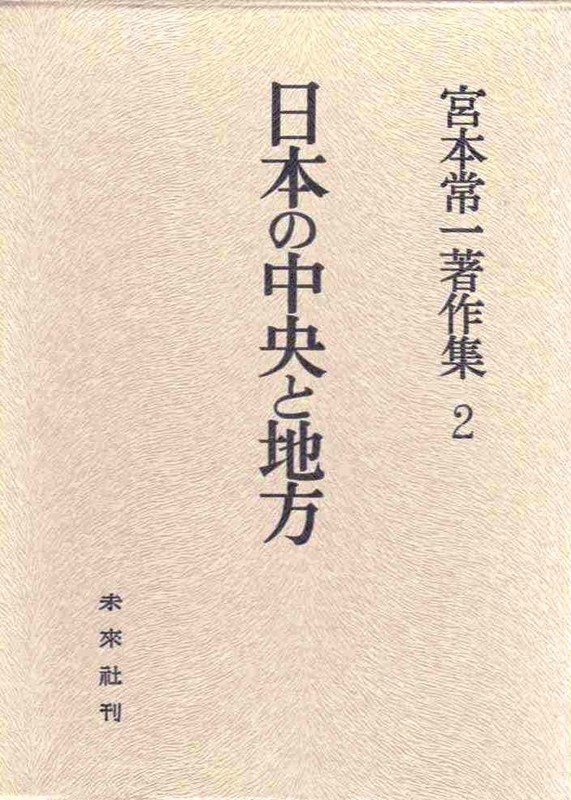
9月から開始する「宮本常一」の著作を読む会の新テキストです。
「日本の中央と地方」著作集2 未来社
当時から農村をはじめ
地方の衰退を歴史的に捉えています。
地方の衰退を歴史的に捉えています。
中央と地方の格差、
あるいは地方間格差がどのようにして生まれ、
それを放置した政治に鋭い目が注ぎこまれています。
あるいは地方間格差がどのようにして生まれ、
それを放置した政治に鋭い目が注ぎこまれています。
私が解説するよりも「あとがき」を
直接読んでもらった方が良さそうです。
直接読んでもらった方が良さそうです。
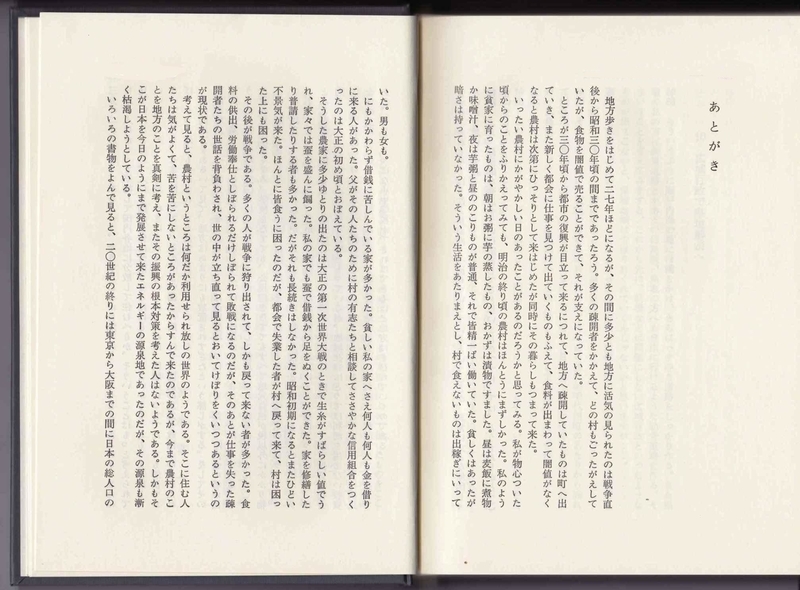
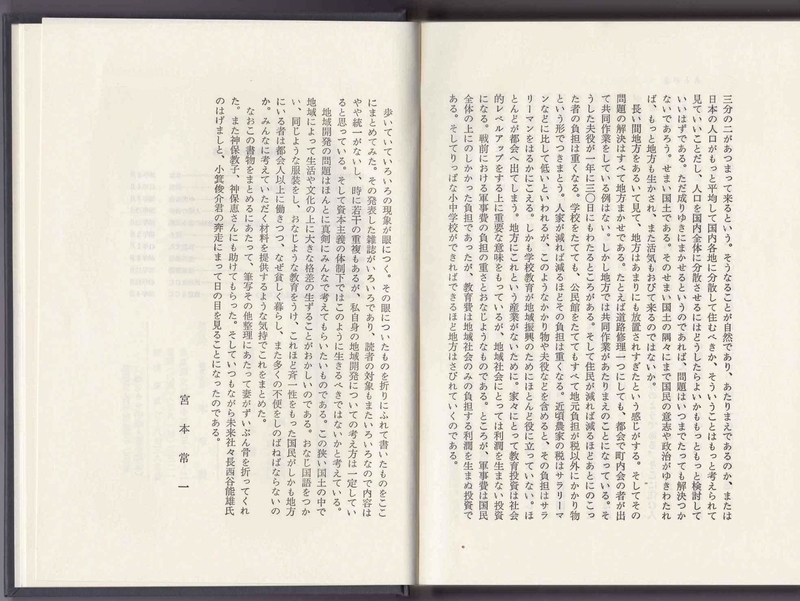
【テキストで読みたい方はこちらをどうぞ】
あとがき
地方歩きをはじめて二七年ほどになるが、その間に多少とも地方に活気の見られたのは戦争直後から昭和三〇年頃の間までであったろう。多くの疎開者をかかえて、どの村もごったがえしていたが、食物を闇値で売ることができて、それが支えになっていた。
ところが三〇年頃から都市の復興が目立って来るにつれて、地方へ疎開していたものは町へ出ていき、また新しく都会に仕事を見つけて出ていくものもふえて、食料が出まわって闇値がなくなると農村は次第にひっそりとして来はじめたが同時にその暮らしもつまって来た。
いったい農村にかがやかしい日のあったことがあるのだろうかと思ってみる。私が物心ついた頃からのことをふりかえってみても、明治の終り頃の農村はほんとうにまずしかった。私のように貧家に育ったものは、朝はお粥に芋の蒸したもの、おかずは潰物ですました。昼は麦飯に煮物か味噌汁、夜は芋粥と昼ののこりものが普通、それで皆精一ぱい働いていた。貧しくはあったが咄さは持っていなかった。そういう生活をあたりまえとし、村で食えないものは出稼ぎにいっていた。男も女も。
にもかかわらず借銭に苦しんでいる家が多かった。貧しい私の家へさえ何人も何人も金を借りに来る人があった。父がその人たちのために村の有志たちと相談してささやかな信用組合をつくったのは大正の初め頃とおぽえている。
そうした農家に多少ゆとりの出たのは大正の第一次世界大戦のときで生糸がすばらしい値でうれ、家々では蚕を盛んに飼った。私の家でも蚕で借銭から足をぬくことができた。家を修繕したり普請したりする者も多かった。だがそれも長続きはしなかった。昭和初期になるとまたひどい不景気が来た。ほんとに皆食うに困ったのだが、都会で失業した者が村へ戻って来て、村は困った上にも困った。
その後が戦争である。多くの人が戦争に狩り出されて、しかも戻って来ない者が多かった。食料の供出、労働奉仕としぼられるだけしぼられて敗戦になるのだが、そのあとが仕事を失った疎開者たちの世話を背負わされ、世の中が立ち直って見るとおいてけぽりをくいつつあるというのが現状である。
考えて見ると、農村というところは何だか利用せられ放しの世界のようである。そこに住む人たちは気がよくて、苦を苦にしないところがあったからすんで来たのであるが、今まで農村のこ
とを地方のことを真剣に考え、またその振興の根本対策を考えた人はないようである。しかもそこが日本を今日のようにまで発展させて来たエネルギーの源泉地であったのだが、その源泉も漸く枯渇しようとしている。
いろいろの書物をよんで見ると、二〇世紀の終りには東京から大阪までの間に日本の総人口の三分の二があつまって来るという。そうなることが自然であり、あたりまえであるのか、またはロ本の人口がもっと平均して国内各地に分散して住むべきか、そういうことはもっと考えられて見ていいことだし、人口を国内全体に分散させるにはどうしたらよいかももっともっと検討していいはずである。ただ成りゆきにまかせるというのであれば、問題はいつまでたっても解決つかないであろう。せまい国土である。そのせまい国土の隅々にまで国民の意志や政治がゆきわたれば、もっと地方も生かされ、また活気もおぴて来るのではないか。
`
長い間地方をあるいて見て、地方はあまりにも放置されすぎたという感じがする。そしてその問題の解決はすべて地方まかせである。たとえば道路修理一つにしても、都会で町内会の者が出て共同作業をしている例はない。しかし地方では共同作業があたりまえのことになっている。そうした夫役が一年に三〇日にもわたるところがある。そして住民が減れば減るほどあとにのこった者の負担は重くなる。学校をたてても、公民館をたててもすべて地元負担が税以外にかかり物という形でつきまとう。人家が減れば減るほどその負担は重くなる。近頃農家の税はサラリーマンなどに比して低いといわれるが、このようなかかり物や夫役などを含めると、その負担はサラリーマンをはるかにこえる。しかも学校教育が地域振興のためにほとんど役に立っていない。ほとんどが都会へ出てしまう。地方にこれという産業がないために。家々にとって教育投資は社会的レベルア″プをする上に重要な意味をもっているが、地域社会にとっては利潤を生まない投資になる。戦前における軍事費の負担の重さとおなじようなものである。ところが、軍事費は国民全体の上にのしかかった負担であったが、教育費は地域社会のみの負担する利潤を生まぬ投資である。そしてりっぱな小中学校ができればできるほど地方はさぴれていくのである。
歩いていていろいろの現象が服につく。その服についたものを折りにふれて書いたものをここにまとめてみた。その発表した雑誌がいろいろであり、読者の対象もまたいろいろなので内容はやや統一がないし、時に若干の重複もあるが、私自身の地域開発についての考え方は一定していると思っている。そして資本主義の体制下ではこのように生きるべきではないかと考えている。
地域開発の問題はほんとに真剣にみんなで考えてもらいたいものである。この狭い国土の中で地域によって生活や文化の上に大きな格差の生ずることがおかしいのである。おなじ国語をつかい、同じような服装をし、おなじような教育をうけ、これほど斉一性をもった国民がしかも地方にいる者は都会人以上に働きつつ、なぜ貧しく暮らし、また多くの不便をしのばねばならないのか。みんなに考えていただく材料を提供するような気持でこれをまとめた。
なおこの書物をまとめるにあたって、筆写その他整理にあたって妻がずいぶん骨を折ってくれた。また神保教子、神保恵さんにも助けてもらった。そしていつもながら未来社々長西谷能雄氏のはげましと、小箕俊介君の奔走にまって日の目を見ることになったのである。
宮本常一
☆★☆★☆★☆★☆★
742-2922 山口県周防大島町沖家室島
有限会社 沖家室水産
民宿 鯛の里(コイの里ではありません。タイの里です。タ・イッ!! )
0820-78-2163 松本昭司
shouji@d3.dion.ne.jp
★島のお買いもの便 http://www.d3.dion.ne.jp/~shouji/okaimono.htm
★「よう来たのんた沖家室」http://www.h3.dion.ne.jp/~kamuro/
★鯛の里HP http://www.d3.dion.ne.jp/~shouji/tainosato.htm
あとがき
地方歩きをはじめて二七年ほどになるが、その間に多少とも地方に活気の見られたのは戦争直後から昭和三〇年頃の間までであったろう。多くの疎開者をかかえて、どの村もごったがえしていたが、食物を闇値で売ることができて、それが支えになっていた。
ところが三〇年頃から都市の復興が目立って来るにつれて、地方へ疎開していたものは町へ出ていき、また新しく都会に仕事を見つけて出ていくものもふえて、食料が出まわって闇値がなくなると農村は次第にひっそりとして来はじめたが同時にその暮らしもつまって来た。
いったい農村にかがやかしい日のあったことがあるのだろうかと思ってみる。私が物心ついた頃からのことをふりかえってみても、明治の終り頃の農村はほんとうにまずしかった。私のように貧家に育ったものは、朝はお粥に芋の蒸したもの、おかずは潰物ですました。昼は麦飯に煮物か味噌汁、夜は芋粥と昼ののこりものが普通、それで皆精一ぱい働いていた。貧しくはあったが咄さは持っていなかった。そういう生活をあたりまえとし、村で食えないものは出稼ぎにいっていた。男も女も。
にもかかわらず借銭に苦しんでいる家が多かった。貧しい私の家へさえ何人も何人も金を借りに来る人があった。父がその人たちのために村の有志たちと相談してささやかな信用組合をつくったのは大正の初め頃とおぽえている。
そうした農家に多少ゆとりの出たのは大正の第一次世界大戦のときで生糸がすばらしい値でうれ、家々では蚕を盛んに飼った。私の家でも蚕で借銭から足をぬくことができた。家を修繕したり普請したりする者も多かった。だがそれも長続きはしなかった。昭和初期になるとまたひどい不景気が来た。ほんとに皆食うに困ったのだが、都会で失業した者が村へ戻って来て、村は困った上にも困った。
その後が戦争である。多くの人が戦争に狩り出されて、しかも戻って来ない者が多かった。食料の供出、労働奉仕としぼられるだけしぼられて敗戦になるのだが、そのあとが仕事を失った疎開者たちの世話を背負わされ、世の中が立ち直って見るとおいてけぽりをくいつつあるというのが現状である。
考えて見ると、農村というところは何だか利用せられ放しの世界のようである。そこに住む人たちは気がよくて、苦を苦にしないところがあったからすんで来たのであるが、今まで農村のこ
とを地方のことを真剣に考え、またその振興の根本対策を考えた人はないようである。しかもそこが日本を今日のようにまで発展させて来たエネルギーの源泉地であったのだが、その源泉も漸く枯渇しようとしている。
いろいろの書物をよんで見ると、二〇世紀の終りには東京から大阪までの間に日本の総人口の三分の二があつまって来るという。そうなることが自然であり、あたりまえであるのか、またはロ本の人口がもっと平均して国内各地に分散して住むべきか、そういうことはもっと考えられて見ていいことだし、人口を国内全体に分散させるにはどうしたらよいかももっともっと検討していいはずである。ただ成りゆきにまかせるというのであれば、問題はいつまでたっても解決つかないであろう。せまい国土である。そのせまい国土の隅々にまで国民の意志や政治がゆきわたれば、もっと地方も生かされ、また活気もおぴて来るのではないか。
`
長い間地方をあるいて見て、地方はあまりにも放置されすぎたという感じがする。そしてその問題の解決はすべて地方まかせである。たとえば道路修理一つにしても、都会で町内会の者が出て共同作業をしている例はない。しかし地方では共同作業があたりまえのことになっている。そうした夫役が一年に三〇日にもわたるところがある。そして住民が減れば減るほどあとにのこった者の負担は重くなる。学校をたてても、公民館をたててもすべて地元負担が税以外にかかり物という形でつきまとう。人家が減れば減るほどその負担は重くなる。近頃農家の税はサラリーマンなどに比して低いといわれるが、このようなかかり物や夫役などを含めると、その負担はサラリーマンをはるかにこえる。しかも学校教育が地域振興のためにほとんど役に立っていない。ほとんどが都会へ出てしまう。地方にこれという産業がないために。家々にとって教育投資は社会的レベルア″プをする上に重要な意味をもっているが、地域社会にとっては利潤を生まない投資になる。戦前における軍事費の負担の重さとおなじようなものである。ところが、軍事費は国民全体の上にのしかかった負担であったが、教育費は地域社会のみの負担する利潤を生まぬ投資である。そしてりっぱな小中学校ができればできるほど地方はさぴれていくのである。
歩いていていろいろの現象が服につく。その服についたものを折りにふれて書いたものをここにまとめてみた。その発表した雑誌がいろいろであり、読者の対象もまたいろいろなので内容はやや統一がないし、時に若干の重複もあるが、私自身の地域開発についての考え方は一定していると思っている。そして資本主義の体制下ではこのように生きるべきではないかと考えている。
地域開発の問題はほんとに真剣にみんなで考えてもらいたいものである。この狭い国土の中で地域によって生活や文化の上に大きな格差の生ずることがおかしいのである。おなじ国語をつかい、同じような服装をし、おなじような教育をうけ、これほど斉一性をもった国民がしかも地方にいる者は都会人以上に働きつつ、なぜ貧しく暮らし、また多くの不便をしのばねばならないのか。みんなに考えていただく材料を提供するような気持でこれをまとめた。
なおこの書物をまとめるにあたって、筆写その他整理にあたって妻がずいぶん骨を折ってくれた。また神保教子、神保恵さんにも助けてもらった。そしていつもながら未来社々長西谷能雄氏のはげましと、小箕俊介君の奔走にまって日の目を見ることになったのである。
宮本常一
☆★☆★☆★☆★☆★
742-2922 山口県周防大島町沖家室島
有限会社 沖家室水産
民宿 鯛の里(コイの里ではありません。タイの里です。タ・イッ!! )
0820-78-2163 松本昭司
shouji@d3.dion.ne.jp
★島のお買いもの便 http://www.d3.dion.ne.jp/~shouji/okaimono.htm
★「よう来たのんた沖家室」http://www.h3.dion.ne.jp/~kamuro/
★鯛の里HP http://www.d3.dion.ne.jp/~shouji/tainosato.htm